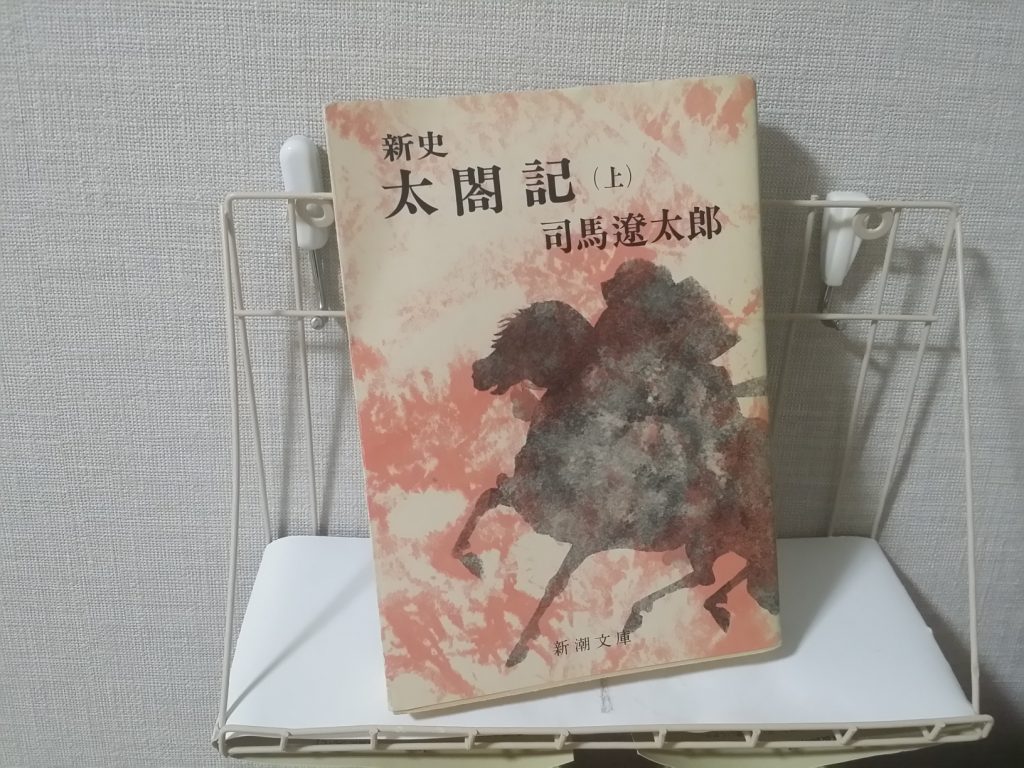上下巻を合わせて、読み切るのに、結構な時間がかかった。この小説は、たしかに文庫本としては2冊だが、上巻だけで450ページもある。しかしながら、読んでいて時間を忘れるほど夢中になれる。地下鉄の降りるべき駅の到着が早く感じるのは、良い作品である証拠だ。最近、ようやく歴史小説の面白さを理解できてきたような気がする。中年のおっさんになり、日本の各地を旅したり、戦国武将の個別の物語を断片的に聞きかじっているなど、雑多で余分なことを含めて色々な知識が付いてきてはじめて、歴史小説の醍醐味が味わえるようになるのだと思う。
さて、下巻では、いよいよ藤吉郎が「猿」とは(ほとんど)呼ばれることもなく、筑前の守(かみ)、秀吉、という呼称が馴染んでくる頃のお話である。主君である織田信長が倒され、ひと時は大いに動転するが、これを大いなる機会であると心に決め、今まで日本国では誰も成し遂げたことの無かった「天下統一」を意識しながら歩き始める物語だ。
彼の良いライバルである徳川家康が本格的に登場してくる点も面白い。とても慎重な、時には陰鬱にも思える用心深い徳川家康の描写と、それとはまったく好対照な豊臣秀吉の機転、快活さが面白い。秀吉の、お供の者をほとんど付けずに、危険な場所や状況にほぼ単身で歩き挑んでいく大胆さもスゴイが、それに対して「ここで彼を殺しては名がすたる」と感じてしまう敵方の日本的な美意識、武士としてのプライドのようなものがあり、それらが心理的にぶつかる状況が、たまらなく日本的で好きになる。
秀吉の柔軟な頭の切り替えが素晴らしい。最近で言う、イノベーションであろう。攻城戦を「土木工事」と見立てて、今までの常識をまったく変えてしまうような考え方や、商業を大事にして「石高よりも金」と考える侍らしくないところなど。もともと農民の出自で、代々の家来を持たない点、貴族に対する憧れを抱いている点など、とても切なくすら感じる。
調略活動や深謀知略を自在に活用し、敵方にとっては油断のならない豊臣秀吉は、後年の行動も含めて、どこか暗い印象を受けやすい。一方で、本作品では、とことんに無邪気であり、憎めず、一途な点が魅力的に書かれている。一世一代の大芝居、狂言でもって日本国を取りまとめ、前代未聞の大業を成し遂げた。この小説は、ライバルである徳川家康との友情のようなものが再び咲いたところで筆を置き、彼の没する13年も前で終わっている。最後の彼の一句が、本当に彼の人生を言い表しているようだ。余韻を残しつつ、司馬遼太郎は別の作品へと読者を誘う。
「露と置き露と消えぬるわが身かな 浪華(なにわ)のことは夢のまた夢」