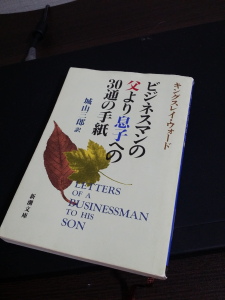
7つの会社を経営する社長である著者は、大病を患って2度にわたる手術を受け、「生きているうちにこれだけは息子に伝えなくては」と思い、30通の手紙を作り始めるようになる。1970年代のカナダでの話のようだ。息子が高校生になり、大学へ進み、会社へ就職し、管理職となり、社長、後継者として成長していくステップの中で、あたかもその時代に存在し、そこで発生する出来事を想定して、手紙が書かれている。
喜多川泰さんの「上京物語」の推薦図書のひとつ。彼の著書である「手紙屋」は、この作品にきっかけがあったのかもしれない。父親からの手紙は、どれもユーモアに富んでおり、大事なこと、愛情に溢れている。部下との衝突、結婚、私的な金銭感覚、友情、批判、ライフバランスなど。どれも一つずつが、大事なテーマで、気づかせられる点が多い。
最後の30章の、「人生の作法」という一説が好きだ。「宴席で作法を守るように、人生の作法を守ることを忘れてはならない。ご馳走がまわってきて、自分の前にきたら、手を伸ばして、礼儀正しく一人分を取る。」まだまわってきていないうちから欲しがったり、次にまわってくるのを滞らせたりしないように。子供、妻、地位、富についても同じである、と言っている。それは著者が引退するという節で、「あとは君に任せる」と題してある。
この本の著者も、例外なく、たいへんな読書家だったようだ。色々な大事な過去の偉人たちの言葉が、この本には散りばめられている。引退後の生活も魅力的である。カナダの大自然に囲まれて、こんな素晴らしい老後がおくれるのなら、なんて幸せだろう。しかしその描写も、息子に対する愛情表現の一つではないか、という気持ちにもなってくる。随所に愛情が溢れている、気持ちの暖かくなる一冊だ。



