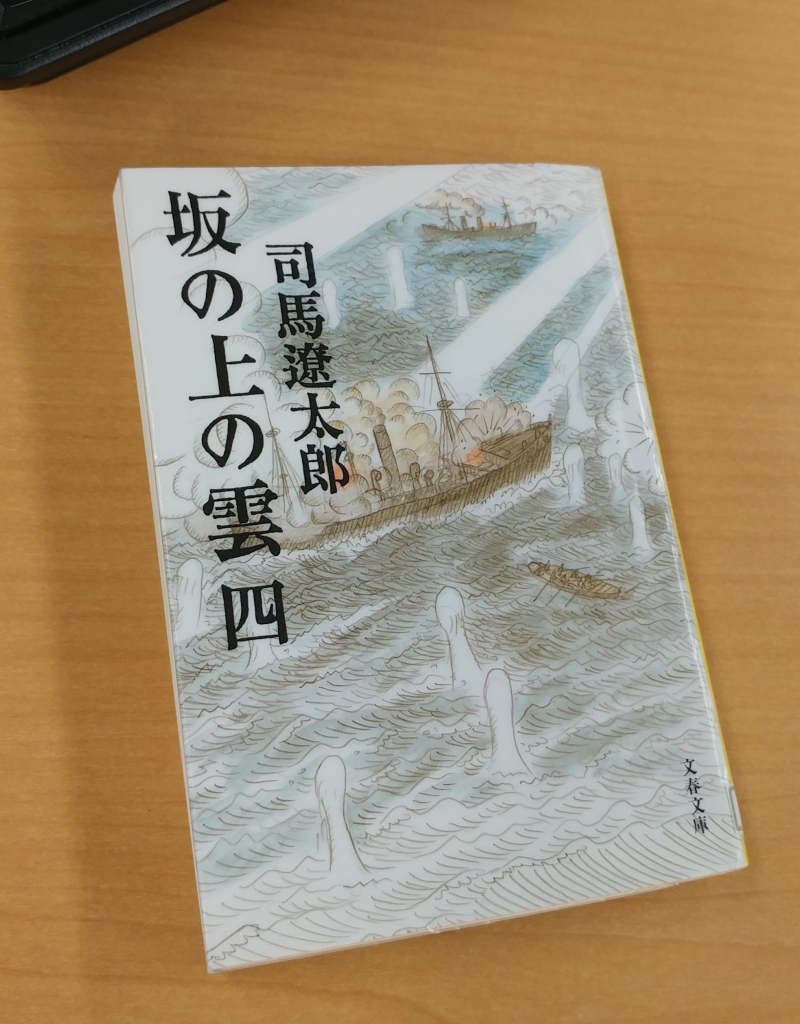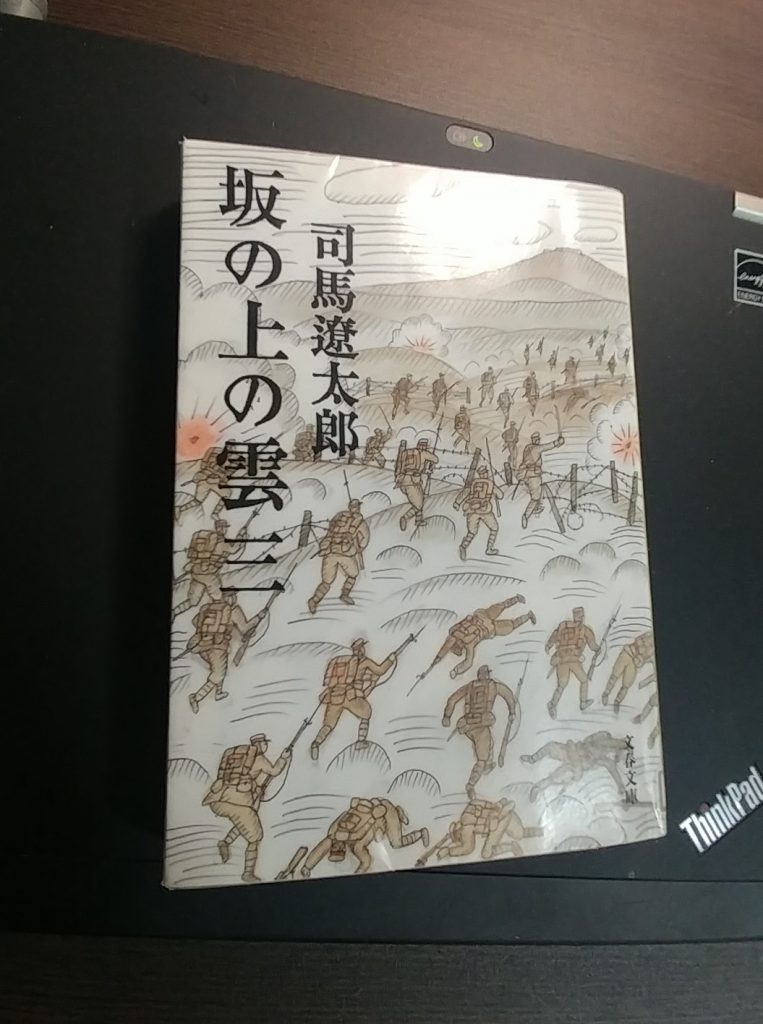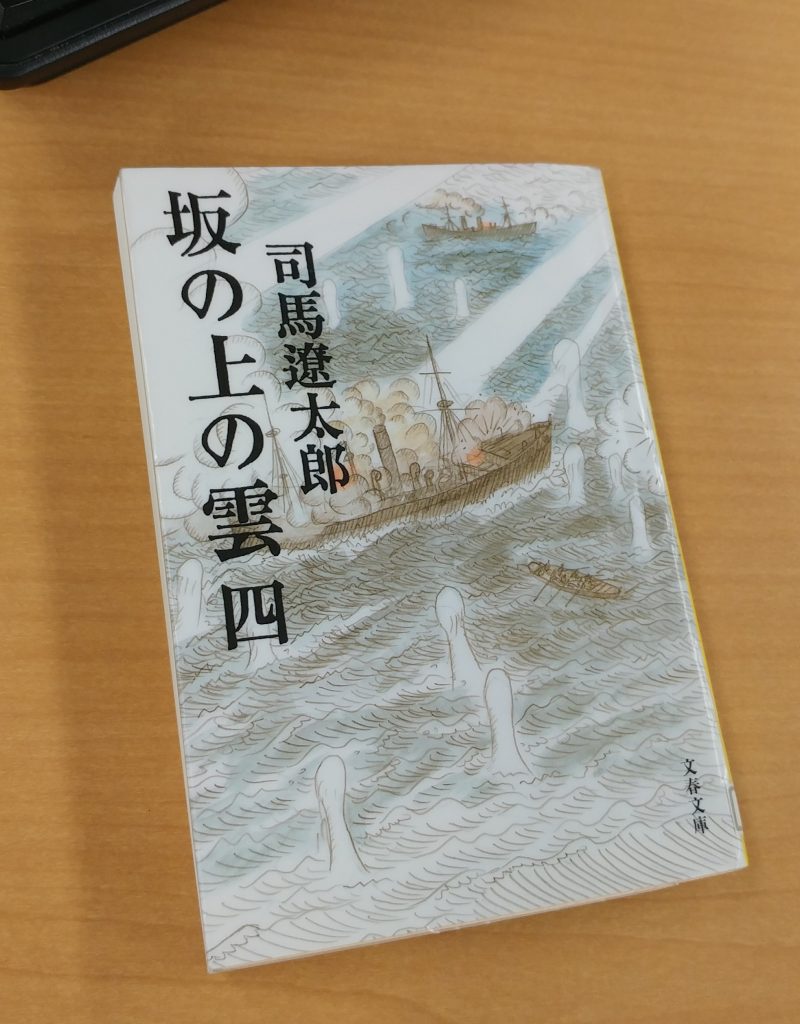
第4巻では、いよいよ日露戦争における両軍の衝突が激しくなってくる。ロシア軍が守る旅順要塞を攻める日本海軍。東郷平八郎が率いる連合艦隊が、黄海海戦、日本海海戦で、物量に勝るロシア軍に勝利する。その要因のひとつとして、「下瀬火薬」が登場する。これがすさまじい威力のある火薬で、「日本の火薬はすごい」とロシア水平に恐れられたそうだ。明治の開国から30年、全く新しい火薬を発明してしまう日本の強さが、誇らしかった。弱国の日本が勝つには、全く新しい兵器の開発が必要と考え、研究所でも「模倣よりも発明を重んじる風」があったそうだ。このような気風が、日本人がノーベル賞を多く受賞していくことに繋がったのだと思う。
遼東半島を部隊とした日露戦争は、まず海軍による旅順(遼東半島の先端にある。今の大連市旅順口区)を巡る海戦に始まる。ロシア軍の太平洋艦隊を、堅固な要塞である旅順へ封鎖し、その間に陸軍は朝鮮半島を経由して遼東半島の内陸部へ上陸。日露はじめての大規模な会戦である「遼陽会戦」、さらに奉天(いまの遼寧省瀋陽市)へと続く太子河を渡っての「沙河会戦」が展開され、両軍とも10万人規模の死傷者を出す。やがて「旅順総攻撃」へと繋がっていく。
表紙の絵が表しているように、1巻分ほぼ丸ごと、日露戦争での両軍の激突について記載している。当時の日本の軍隊の状態について子細であり、いかに資源の少ない状態で、実に難しい戦争に挑んだのかということが語られる。特に陸軍の無茶な補給線や、藩閥政治に由来する無謀な指揮官の任命など、小説的な要素を少なからず含んでいるとは言え、それが太平洋戦争まで続いた陸軍の悪しき根源であるかのように書かれている。
一方で、ロシアのバルチック艦隊が出港し、日本海へと向かう行程については、的確ではない将校に率いられるロシア水兵に対しては大変に気の毒ではあるが、ずいぶんと滑稽に描かれている。ロシアから地中海を経て、随分と遠くの日本海戦まで来なくてはいけない状況自体、気の毒であるように思える。英国海軍の強さも端々に見える。それにつけても、ロシアという大国の圧倒的な国力を有する国に戦争を宣言した当時の日本の状況の、瀬戸際の感じが、ハラハラする。
旅順総攻撃の章では、乃木大将、特に伊地知参謀の愚かしい采配が不愉快でたまらなくなる。史実はどうであったにせよ、この小説の中では完全な悪役であり、愚かな司令官であり、もう、なんともし難い役割を与えられている。
ところで、資源の少ないという点は、今の日本も、さほど状況は変わっていないと思う。もしも今後、米中という二大資源大国に挟まれながらも、これらに脅威を感じつつも、日本が対等なパートナーとして国際社会で切磋琢磨していくためには、第二の明治維新が必要なのかもしれない。