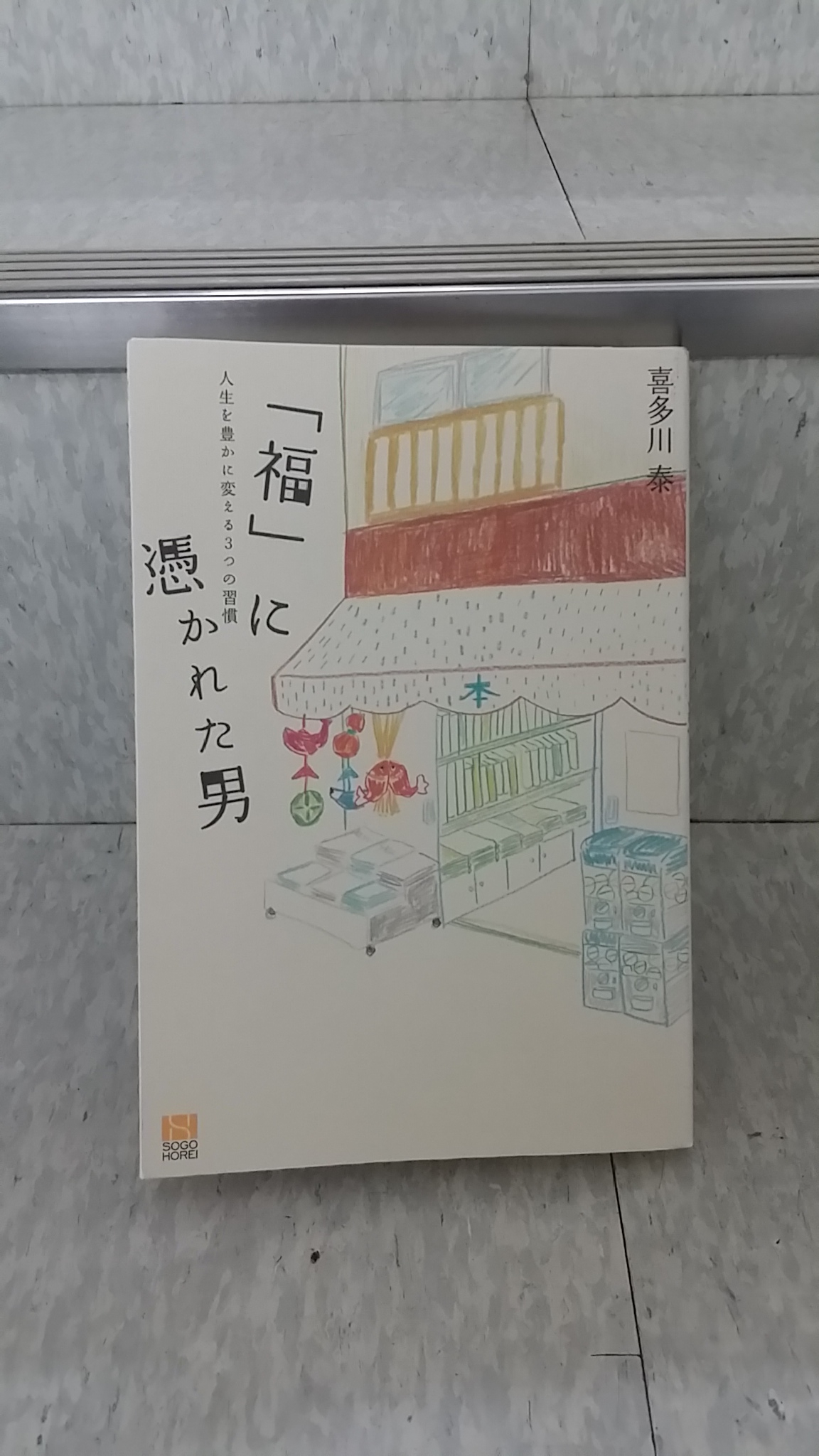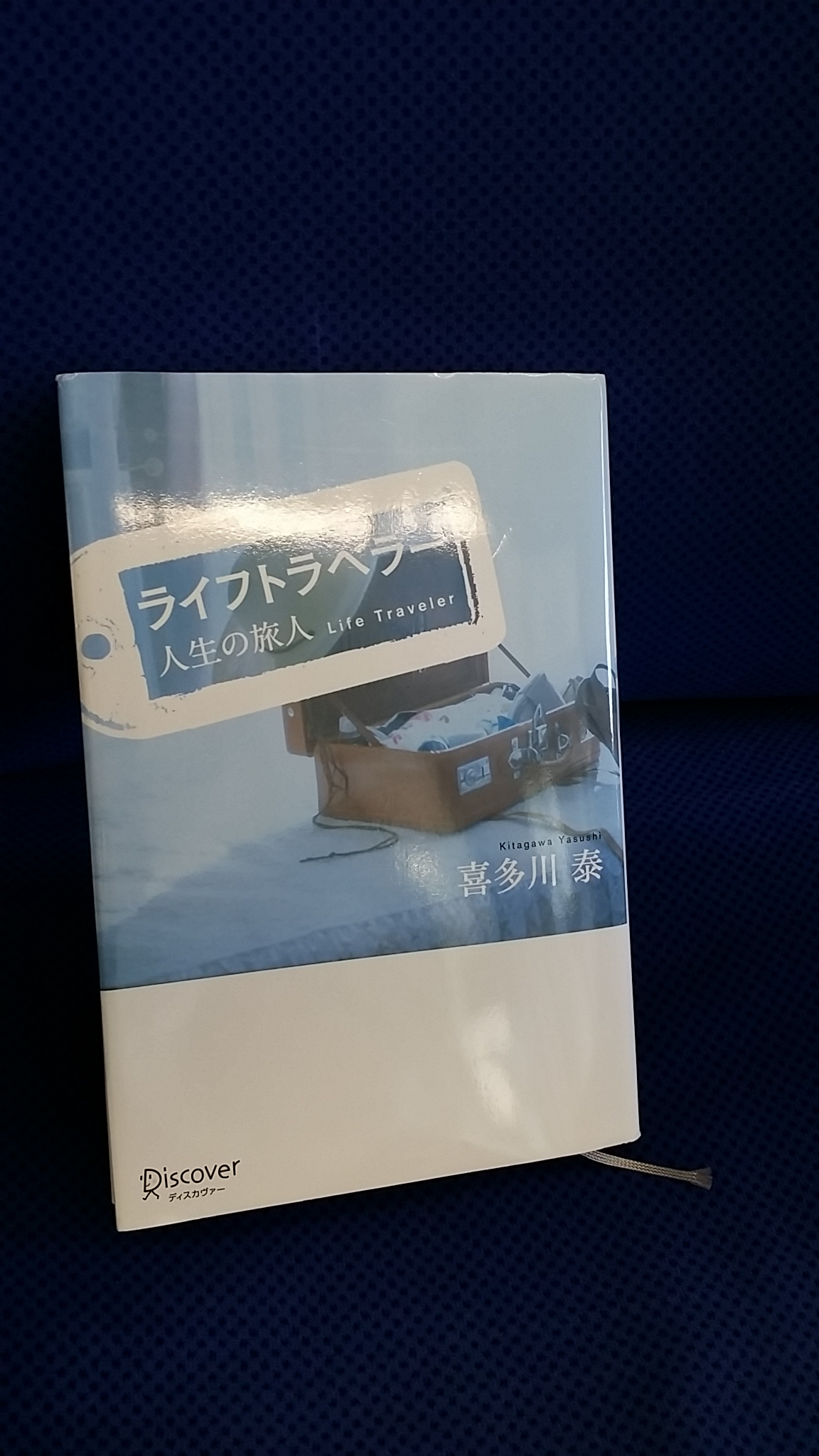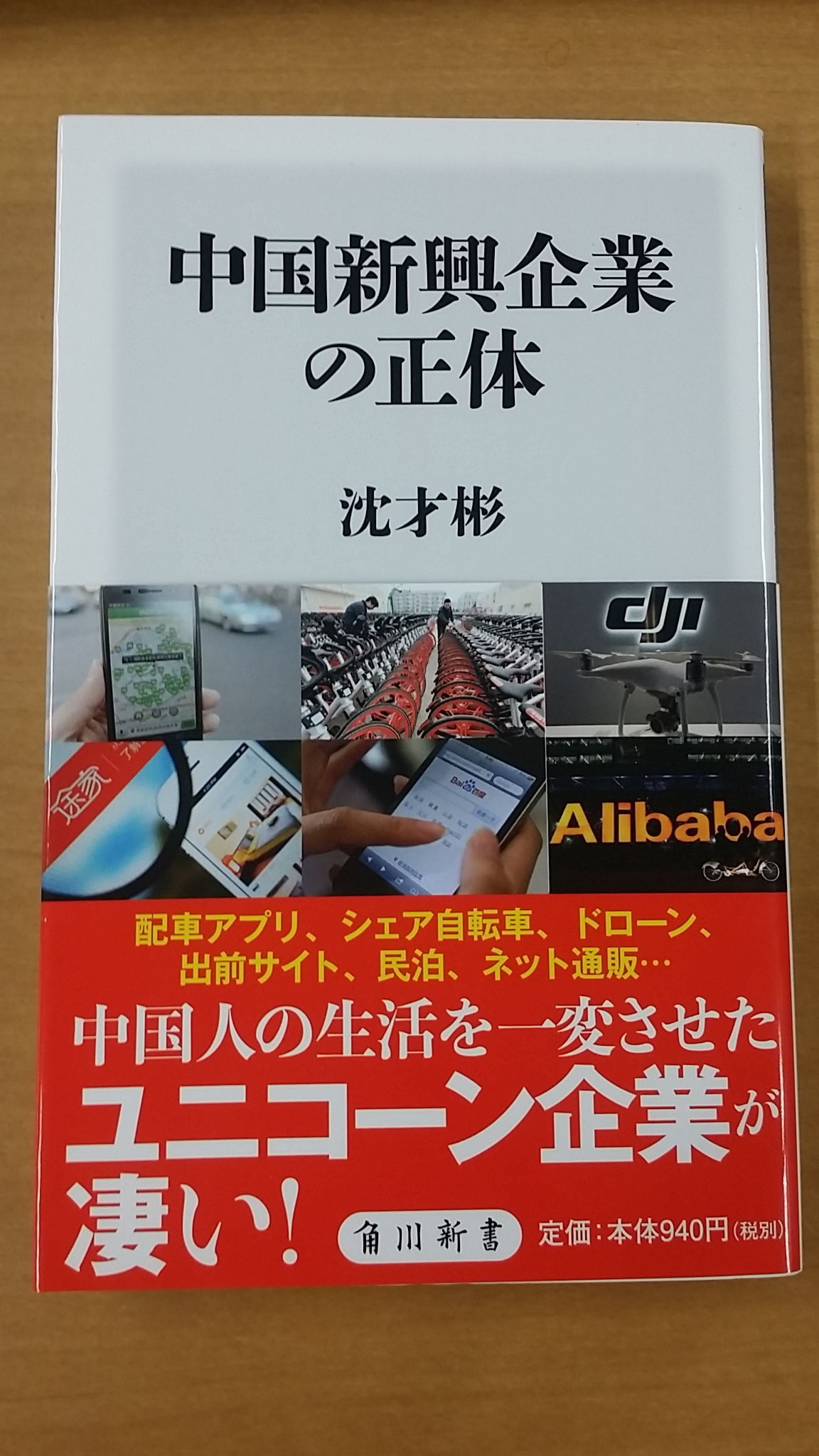会社勤めを経て、父親の書店を継いだ主人公。当初は書店の拡充を目指して情熱を注ぐも、近場での大型書店の開店や、コンビニの新設などが相次ぎ、やる気を失っていた。しかしそれらは、彼にとりついた「福の神」の仕業だった。不思議な縁に取り付かれつつ、「出会い」によって成長していく主人公には愛着が生じる。
会社勤めを経て、父親の書店を継いだ主人公。当初は書店の拡充を目指して情熱を注ぐも、近場での大型書店の開店や、コンビニの新設などが相次ぎ、やる気を失っていた。しかしそれらは、彼にとりついた「福の神」の仕業だった。不思議な縁に取り付かれつつ、「出会い」によって成長していく主人公には愛着が生じる。
福の神が与えるものは「素敵な出会い」。「人間は僕たち福の神が信じられないほど早く成長することができる存在なんだ」という福の神たちの視点も織り交ぜ、テンポよく物語が進む。数々のピンチも、人が成長できるための試練。一方で「受け取る準備のできていない人に対して、数々の成功体験を経験させるのは、貧乏神がよく使う破滅へのプロセスです。」と言い切る。子を思う親心にも同じ傾向を見出して、結果的にその人を幸せから遠ざけてしまうことにもなりますよ、という言葉は親にとっても耳が痛い。福の神の立場では、「その人が受け取ることのできる器に応じた成功を与えること」が「幸せへの最短の方法」なのだそうだ。
「毎月自分は40万円、同僚が30万円」と「自分は50万円、同僚は100万円」の給料で、どちらが「自分は幸せだ。成功している。」と感じるか。自分が豊かであると思えるかどうかということは、手にした富の大きさではない。でも、幸福の基準を他人との比較に置いていると、本当の幸福を見失う。「お金をたくさん稼ぐ」「会社を作る」「大きな家を建てる」といった夢は、本当の夢を実現するための手段でしかない、という。考えるべきは、人生を使って何をするか、ということだと、福の神に疲れた先輩は語る。
生き方のヒントがちりばめられた、ビジネス書でもある。「お客さんをサイフとしか見ていなかった」とは、耳が痛い。著者は当初、精肉店を舞台にしよう、と考えていたようだ。どんな職業であれ、それが何のための仕事か、ということを考えるきっかけを与えてくれる。女性があまり重要な役割を見せないのは、著者の作品にしては珍しい。一方で、著者に似通った登場人物が前面に出て、重要な役割を担っているような作品も、はじめは少し抵抗感もあったが、作品としての目新しさを感じた。