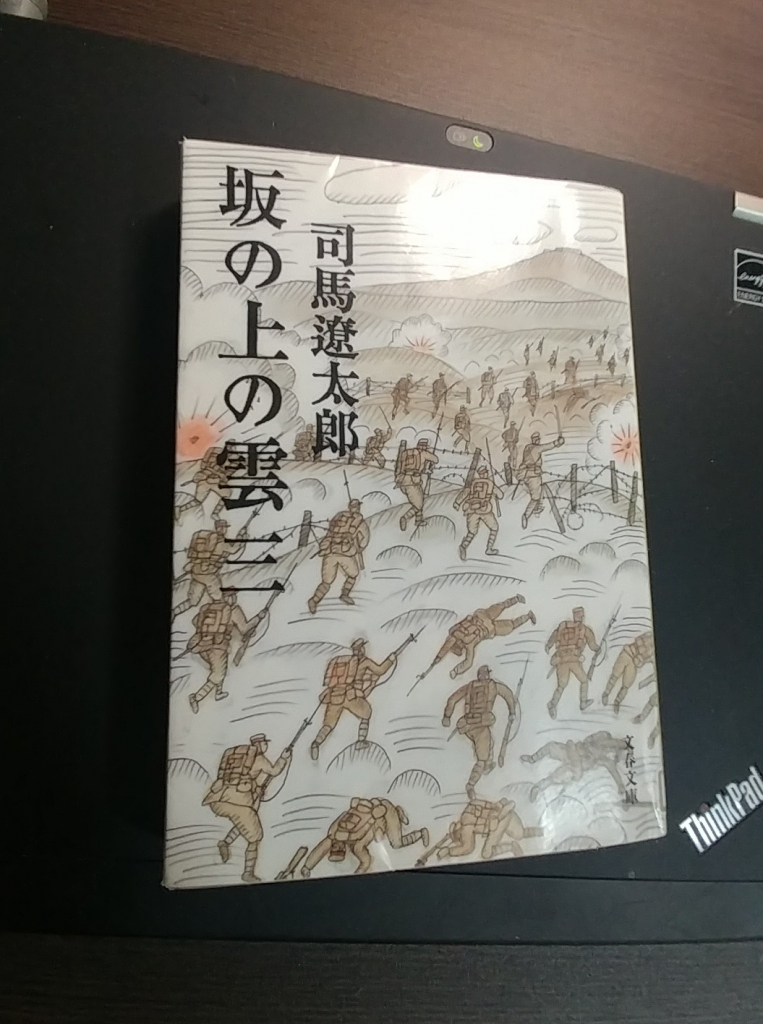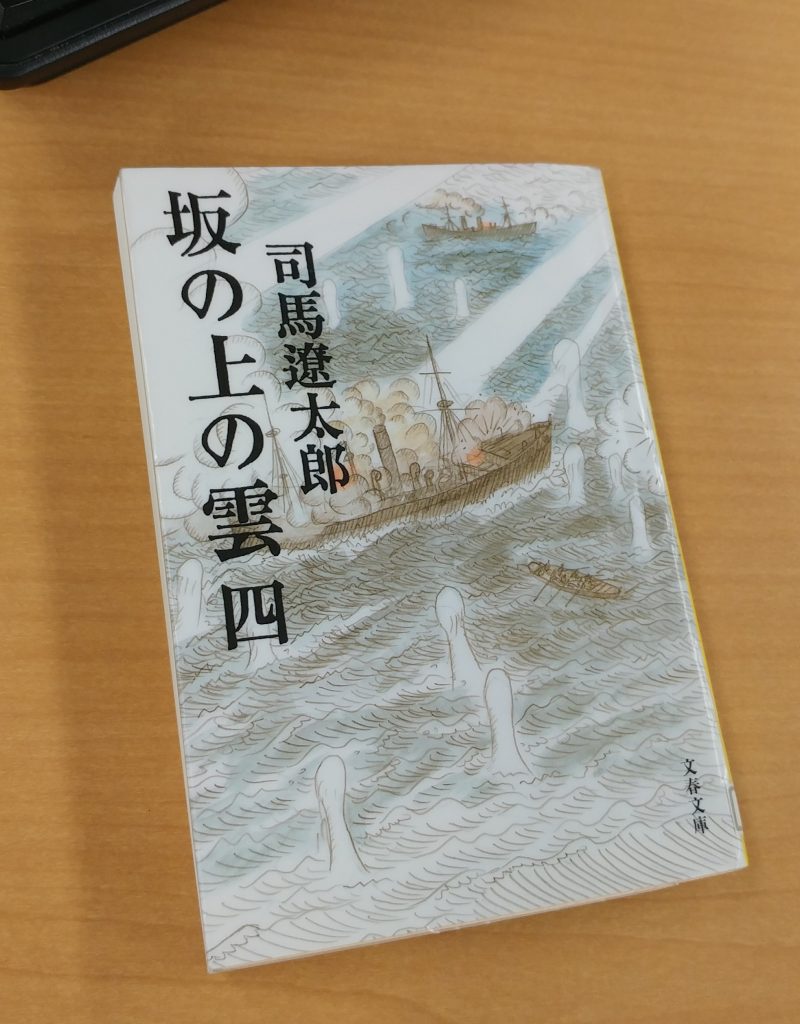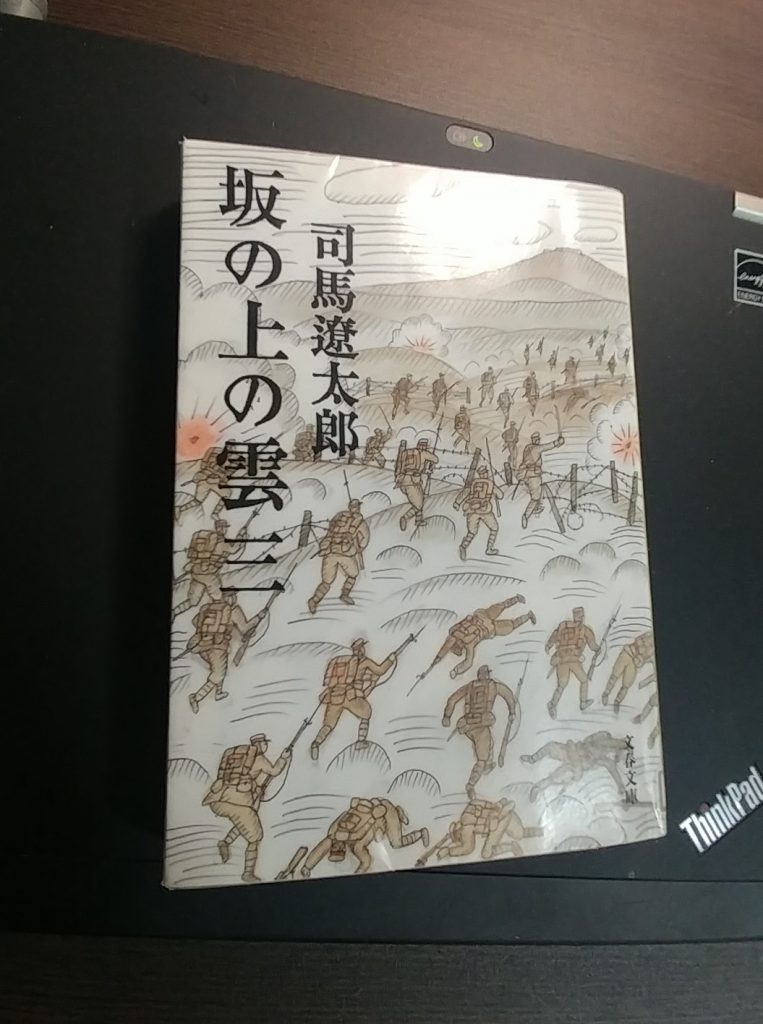
さて、第三巻目を迎える。ほんの数ページを読み進めたところで、正岡子規が亡くなる場面となる。最後まで活発に前向きに、俳句や短歌の文化的な確立に貢献してきたこの主人公が亡くなるにあたって、とても穏やかに描写されている。「十七夜」という章の題名も、合っている。
日清戦争に勝利した明治時代の日本だが、国家の財政は、とても厳しい。日露戦争を迎えるにあたっては、なんと国家財政のほぼ半分が軍事費、という状態だったそうだ。通常の民主主義的な国家であれば国民の反対があり、無理だろう。それでも、ロシアは満州を勝手に占領し、つぎは朝鮮半島を狙っている。そこを選挙されれば、次は日本に来るだろう。ロシアに占拠されたポーランド国民の悲惨な状況を知っているだけに、そのような状態には決してさせたくない。本書によれば、日清戦争、日露戦争、そしてそもそも明治維新までもが、そういった西欧列強に対して日本が「独立」したばっかりに、きわめて短期間のうちに実力をつけていく過程に必然の現象だったように思える。
ふと現代を思うと、たとえばオイルショックだったり、プラザ合意からの円高だったり、果ては東日本大震災もそうかもしれないが、日本人は大自然も含めた「外圧」があると、驚くべき団結と非常な努力により、目を見張るような成長ができる国民性を有しているのではないか、と思えてくる。
騎馬隊を統率する兄の秋山好古、海軍の参謀として東郷平八郎を補佐する弟の秋山真之ともに、遼東半島での実戦を経験する。戦争場面での描写は、冷静にひとつひとつが具体的であり、マンガのような誇張した動作表現は無いのだが、まさに手に汗を握るような迫力がある。日露戦争の緒戦である、旅順閉塞作戦。ロシアとの激しい戦闘の一方で、とくに広瀬武夫という参謀をめぐるロシアとの友情という側面での描写は、ロマンチックで切ない。
小説では、ロシア戦争の諸悪の根源を、ニコライ2世による帝政であるとしている。ロシア軍人の一人ひとりは誠実に描かれており、日本で言う武士道のような騎士のプライドをも持ち合わせているようだ。敵将、例えば老将マカロフなどについても、読者は非常に愛着を持ってしまう。このへんの筆の運び方がとても上手い。戦争の小説で敵方に過度な悪意を抱かせないで、しかも熱中できる展開に引きずり込まれる。緒戦のクライマックスの最中で、第四巻へと続く。