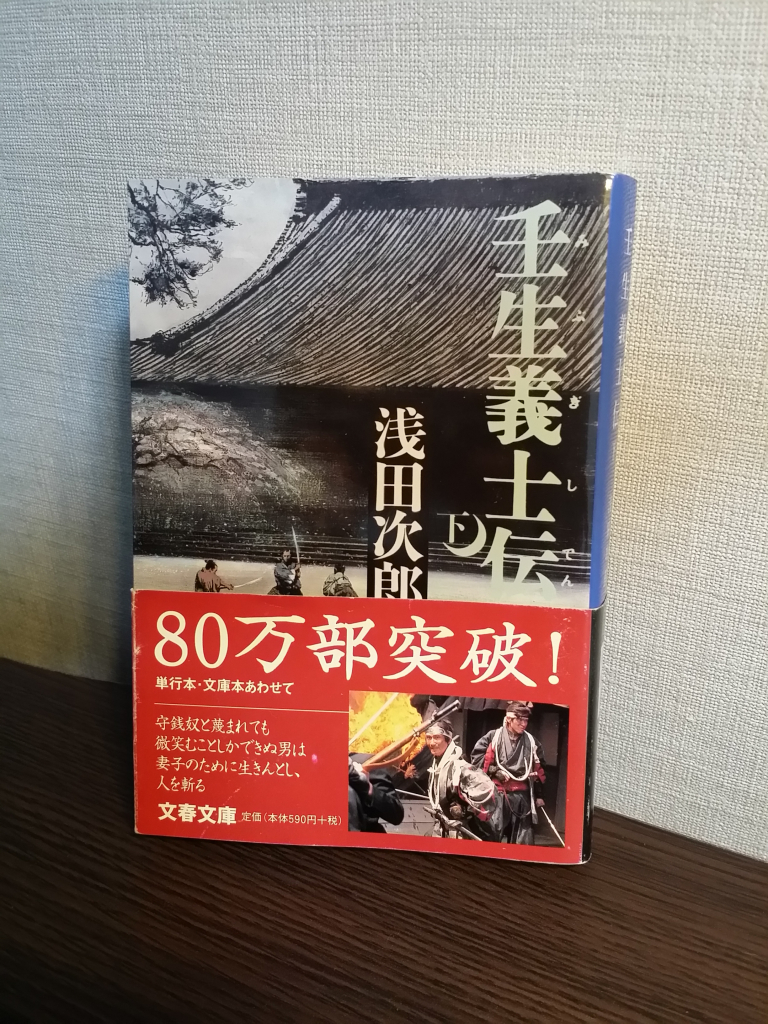浅田次郎による時代小説。下巻では、新撰組が京都で大活躍する事件を描写しつつも、いよいよ薩摩・長州(実際には土佐も)の藩兵が京都へ攻めに上がってくる頃に近づいてくる。
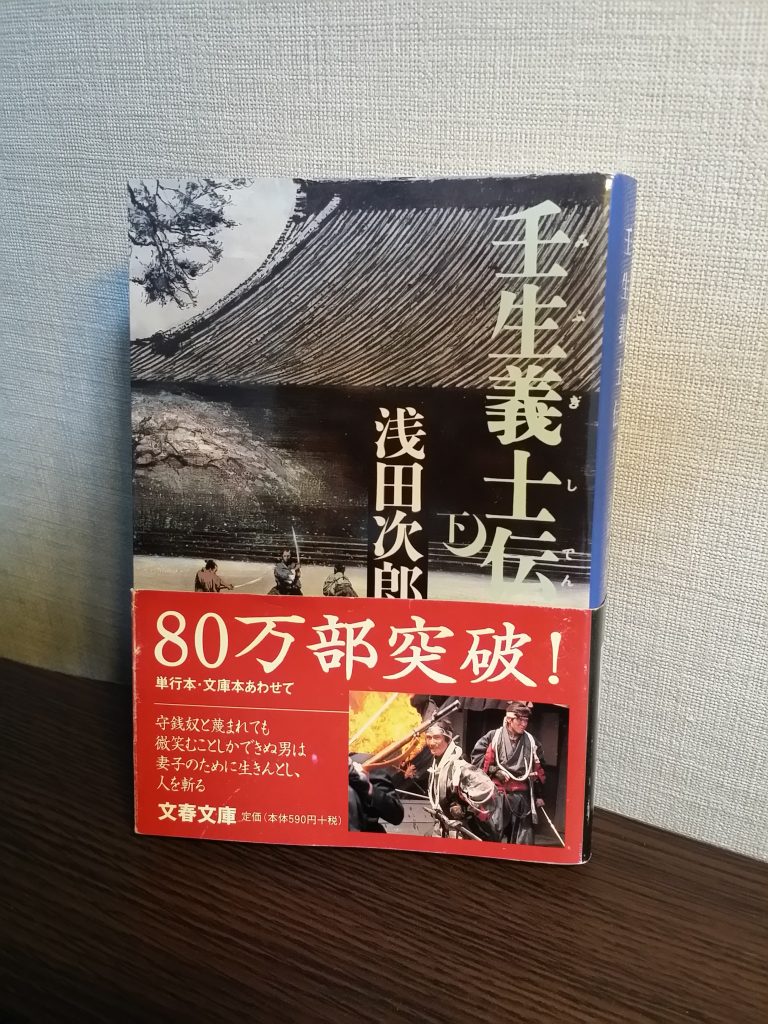
全ての文章が、誰かの語り口で書かれている点は、面白い。この物語の聞き手でもある一人の若者が、様々なところへ赴き、過去に吉村貫一郎に関わったの人たちを訪れたりして、彼らから見聞きした内容が、その時々の相手の一人称で語られている。神保町の酒場の親父さん、会社経営者、商人のご隠居、暴力団組長、町医者など。それぞれの語り口が、それぞれの人物像にとても合致している。浅田次郎氏の作家としての力量なのだと思う。
そして、そういった人々の語りパートと交互に登場する、吉村貫一郎の独自の一人称の語りがある。彼の語る南部弁が、不器用で、無骨で、雰囲気よく、暖かく、心地よい。浅田次郎氏は東京は中野の生まれだという。ここまで雰囲気のある南部弁の描写をできるというのは、作家として、ものすごい力量だと思う。
後半に進むにつれて、だんだん、読んでいて寂しくなってくる。戊辰戦争も後半にさしかかり、徳川幕府を守る側である奥羽列藩(会津を中心とする連合軍)による、新政府軍(薩摩長州)の軍勢への抵抗。時代に対する見方には様々なものがあって然るべきだが、負ける側から描写される時代小説は、どこかもの悲しさを感じてしまう。明治維新を向かえ、誰かを悪者にしなければ収まりがつかない状態だったのだろうか。
一つ心配があったのは、はたして読者は、薩摩や長州が嫌いになってしまうのではないだろうか、と思ってしまう。しかしながら、後半の後半、最後の最後で、戦の最中に、その薩長の藩兵が攻め立てながら、この作品のある重要な人物に対して、涙を流しつつ投げかける言葉に救われる。「君のような義士が、このような戦いで死んでしまうことは、日本国にとって損失である、共に新しい世の中を作ろう」。そして、この小説の結びの部分である。まったく!何なのだろうか、この、浅田次郎という天才は。感動という大波に心を持っていかれてしまう。やられた。古書体の表記は一見して読みづらいけど、キリリとした余韻を残す。日本語の表現の素晴らしさに改めて気がつかせてくれる、大作品だ。